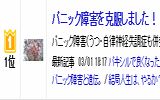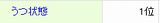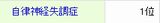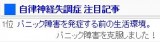低血糖の誤診でパニック障害と診断される場合がある。
という話を聞いてから、誤診について調べてみました。
私はパニック障害と診断されましたが、結局は闘病生活の間、自律神経失調症・月経前症候群・慢性疲労症候群・過呼吸症候群などなど、いろんな病気の可能性も疑ってその克服法を取り入れたりしてみました。
西洋医学は数値の医学ですから、数値的に異常が表れないと診断名がつきません。
なので、もしかしたら少し傾向があるかもしれませんから、自分の症状が当てはまりそうな病気を調べてその克服法を試してみました。
ただ、薬は医師が処方してくれないと飲めませんから、やはり正確な診断をしてもらうということが治癒への第一歩だと思います。
本当はパニック障害なのに、これらの病気に間違えられるという場合もありますし、その逆もありますね。
<パニック障害と間違えられやすい病気>
・心臓神経症
・不安神経症
・自律神経失調症
・メニエール病
・過呼吸症候群
・狭心症
・不整脈
・僧帽弁逸脱症
・側頭葉てんかん
・褐色細胞腫
・バセドウ病
・低血糖
(引用:よくわかる パニック障害・PTSD)
パニック発作では絶対に死なないので、自分で乗り越えるしかないと言われていますが、
その症状がパニック発作ではない場合もありますから、まず体に異常がないか検査をすることはパニック障害を克服する上で非常に重要です。
次回は、9月2日(月)18時更新です。
以前買った本が出てきたので、少しまとめます。
ちなみに私はパニック障害の治療に漢方薬を飲んだことはなく、いろいろな人に勧められましたが、結局処方してくれる医師には出会えませんでした。
ただ、月経前症候群の治療に飲んでいたことはあります。
効果があったかどうかは・・・・・・正直、わかりません。
普段、私たちが病院・医師・医学という場合の医学とは、西洋医学ですよね。
現代ですと、体に不調が起きた場合には、ほとんどの方が西洋医学の病院に行くのではないでしょうか。
もちろん、違う方もいます。
私の知人にも、風邪になった場合にも西洋医学の病院ではなく整体に行くという人がいます。
西洋医学と東洋医学の違いは、
西洋医学は健康状態を数値で測る医学なんですよね。
私は肺炎で死にそうになった経験があるのですが、最初に行った病院で「異常なし!」と判断されたのは、炎症があると増えるはずの白血球の数値が異常ではないからという理由でした。
これに比べ、東洋医学は体を全体として診ます。
また、病気になる前の未病のうちに体の調子を整えることで、病気になりにくい体をつくっていくのが東洋医学の目的です。
どちらが良い・どちらが悪いということではなくて、
それぞれの長所と短所を自分の健康管理にうまく利用したら良いと思います。
東洋医学が好きな方からは何かと批判される西洋医学ですが、救急や怪我の場合には本当に必要な医学ですし、新生児医療にも必要な医学だと思います。
ただ、西洋医学では治らないのではないか?と思われるような病気も昨今は増えているように思いますので、予防医学なんていう言葉もありますが、東洋医学の考え方を取り入れて健康管理をすることも大事なことでしょう。
漢方薬のことだけではなくて、東洋医学の健康の捉え方はとても興味深いですし、パニック障害やうつ・自律神経失調症の方には非常に役立つものだと思います。
漢方ではパニック障害を、「気」や「血」の異常からくると考えるそうです。
東洋医学は奥が深く、なかなか面白いですよ。
次回は、8月26日(月)18時更新です。
パニック障害と低血糖には何か関係はあるのではないか?ということで、少し調べていたりしますが、
実際、みなさん、診断名よりもパニック発作が起きないことのほうが重要ではないでしょうか。
パニック発作の症状と低血糖の症状が似ているというのもありますし、
Twitterのフォロワーさんで、病院の医師に「本当は低血糖なのに、パニック障害と誤診されている人が多い」と言われたという話を聞いたからです。
以前書いた記事は、こちら→パニック障害と低血糖
電車に乗る時・歯医者に行く時・パニック発作が起こりそうな時におすすめグッズで、
第1位で紹介している「バッチフラワー レスキュー・レメディ」ですが、ホメオパシーという、同種療法・同毒療法・同病療法で用いられます。
このホメオパシーというのは、数年前、乳児の死亡事件が起こり社会問題にもなりました。
このレメディですが、ただの砂糖玉ではないか!という論もあるそうで、プラセボ効果しかない!という説もあります。

レメディは飴タイプもあるのですが、私の紹介しているレメディはシロップタイプで、かなり濃縮されたタイプです。
私もなんとなく、これ、ただの砂糖水じゃないかな? と思った時がありますが、
自分では作れないくらい濃縮されているのと、パニック障害と低血糖の関係を考えると、砂糖水でも十分良いわけです。
そして何より、携帯に便利なので、外出時に多いパニック発作にはピッタリです。
パニック障害と低血糖の関係ははっきりしませんが、
調子が悪くなった時に、甘いものを少し摂取すると落ち着くというのは、やはり少し低血糖ぎみなのかもしれません。
何事も試してみなくてはわかりませんので、一度、パニック発作が起きそうな時に試してみてもらいたいものの一つです。
バッチフラワー・レスキューレメディ レビュー
次回は、8月19日(月)18時更新です。
パニック障害と闘うにあたり、精神薬との付き合い方は本当に難しい問題です。
このブログに訪問下さる方は精神薬を服用している方が多いのではないでしょうか。
私も以前は服用していました。
ベンゾジアゼピン系抗不安薬・三環系抗うつ薬・SSRIなどなど。
薬の具体名をあまり覚えていないのが残念なのですが、多い時では1日に50錠以上飲んでいた時もあります。
結局、SSRIであるパキシルとルボックスの副作用で本当に怖ろしい経験をして、私は薬を飲むのは止めよう!と決意したのですが、
薬を飲むことで症状が楽になることも確かですので、上手な付き合い方はないものかと少し考えてみました。

私もそうでしたが、皆さんのお話を聞くと、心療内科や精神科では頓服でお薬を出すというよりも、毎食後・就寝前などに定期的に飲むように処方されることが多いようです。
たぶん、処方される薬がそのように服用することで効果を発揮するのでしょう。
また、うつなどでは、少し良くなったからと自己判断で止めてしまうと再発する恐れがあるので良くなっても少しの間服用しましょうなどとも言われます。
私は医師ではないので、薬に関しては専門的なことはわかりません。
基本的には、処方した医師の指示に従うのがベストだと思います。
ただ、薬を少しでも減らしたい! 薬を止めたい!という方が多いのも事実です。
そういう方はどうしたら良いか?
理想としては、発作が起きそうな時・発作が起きそうな場所に行く時にだけ頓服で薬を飲む。
これだと思います。
発作が苦しいのも事実ですし、薬によって症状が楽になるのも事実です。
いきなり薬を全部やめるのは困難でしょうから、安心のためにも、頓服で薬を持っていたら良いのではないかと思います。
そして、それを、かかりつけの医師に相談してみることです。
私も薬を止めたい!と決意してからは、医師に薬に対しての要望をはっきり言うようにしました。
それまでは、医師に言われるがまま、処方されるがまま飲んでいたのですが、
薬を止める!と決めてからは、
医師が毎食後・就寝前と処方しても「就寝前だけではダメですか?」「調子が良い日は、自分の判断で半分にしてはダメですか?」
などと、なるべく減らすことが出来るように、質問をしました。
おそらく、病気が本当に辛くて大変な時期は、薬を止めたい!という気持ちは湧いてこないと思います。
薬を止めたいなという気持ちが湧いてきたということは、少しずつ病気が回復してきたということでしょうから、医師に自分の要望を伝えてみても良いかもしれません。
薬は、薬にもなるし毒にもなりますから、上手に付き合っていきたいですね。
次回は、6月17日(月)18時更新です。
パニック障害は、心の病なのか? 脳の病なのか? と思う方がいるでしょう。
私は当初、心の病だと思っていました。
心療内科や精神科に行くことから考えて、心の病なのかな。と・・・。
でも闘病生活を続けていくうちに、脳の病ではないか?と思い、脳についても少しですが勉強しました。
Wikipediaによると、近年の研究では心の病ではなくて脳機能障害と扱われているとのことですので、脳の病なのかもしれません。
脳の病というとなんだかすごく大変そうと言いますか、大変な病気だと思いがちですが、
私は、心の病よりは大変ではないのではないか?と思ったりもします。
そもそも、心というものがどこに存在しているのか? 心の病なんてものはないのではないか? と思ったりもしますし、実際そうおっしゃっている方はいますよね。
すべては脳の作用と考えれば、脳の病ということになります。

私は、パニック障害は交感神経の暴走と考えています。
何らかの原因で、交感神経のスイッチがオンになってしまう。
すると、動悸・息切れ・吐き気・めまいなど、交感神経が過剰になった時の症状が体に現れます。
MAXの状態が、このまま死ぬのではないか?という状態です。
おそらく、パニック障害の方は交感神経が過剰になるような生活をこれまで送ってきたのではないでしょうか。
少なくとも私は、心当たりがあります。
交感神経が過剰になるというのは、緊張・不安・集中など戦闘態勢のような状態を言います。
逆に、副交感神経が優位になるというのは、ぼぉ~とした状態・リラックスした状態・ほんわかした状態を言います。
交感神経と副交感神経のバランスがとれているのが健康な状態で、このバランスが崩れると、様々な病気が発現します。
パニック障害の方は、自分が交感神経が優位になりやすいとまずは自覚しましょう!
そして、副交感神経をもう少し優位にするように、意識してみましょう!
副交感神経を優位にするのは、
ぬるめのお湯に浸かったり、気持ちが良いマッサージを受けたり、ぼぉ~っとリラックスした状態を作ることです。
副交感神経を優位にする方法は、他にも思い出しましたら、またメルマガでお知らせしたいと思います。
次回は、6月10日(月)18時更新です。